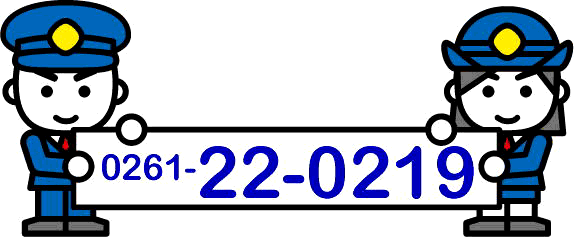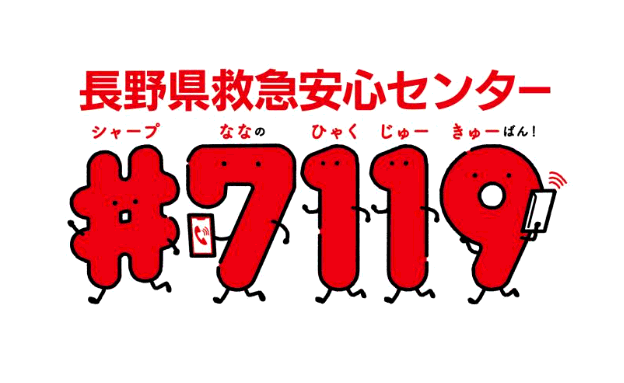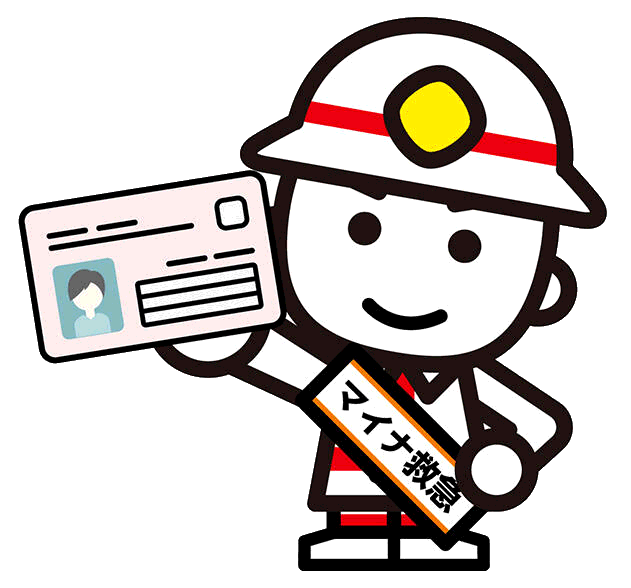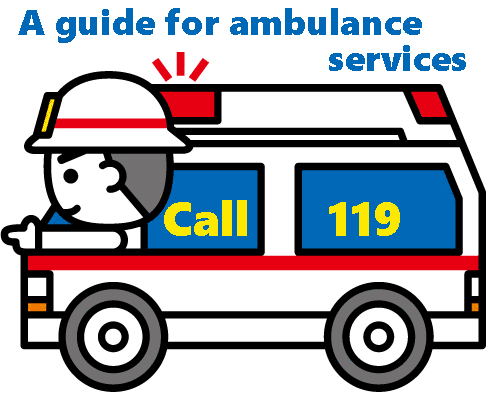車両の紹介
北アルプス広域消防本部には、全部で23台の消防車両・緊急車両が配備されています。代表的な車両を紹介します。
消防ポンプ自動車(CD-Ⅰ)
| 全長 | 5,885mm |  |
|---|
| 全幅 | 1,880mm |
|---|
| 全高 | 2,950mm |
|---|
| 排気量 | 4,009cc |
|---|
| 駆動方式 | パートタイム4WD |
|---|
| ポンプ級 | A-2級ポンプ、フォームプロ搭載 |
|---|
| 水槽容量 | 1,300リットル |
|---|
| 配備署 | 大町消防署(令和4年1月) |
|---|
水槽付消防ポンプ自動車(Ⅰ-A)
| 全長 | 7,300mm |  |
|---|
| 全幅 | 2,310mm |
|---|
| 全高 | 2,980mm |
|---|
| 排気量 | 6,400cc |
|---|
| 駆動方式 | フルタイム4WD |
|---|
| ポンプ級 | A-2級ポンプ、CAFS搭載 |
|---|
| 水槽容量 | 1,500リットル |
|---|
| 配備署 | 北部消防署(平成25年3月) |
|---|
救助工作車(Ⅱ型)
| 全長 | 7,570mm |  |
|---|
| 全幅 | 2,300mm |
|---|
| 全高 | 3,100mm |
|---|
| 排気量 | 6,400ccDターボ |
|---|
| 駆動方式 | パートタイム4WD |
|---|
| 主要装置 | 移動式クレーン、前後ウィンチ |
|---|
| | 600W照明装置 |
|---|
| | 超高圧油圧発生装置 など |
|---|
| 配備署 | 大町消防署(平成20年9月) |
|---|
多目的積載車
| 全長 | 5,590mm |  |
|---|
| 全幅 | 1,930mm |
|---|
| 全高 | 2,700mm |
|---|
| 排気量 | 4,610cc |
|---|
| 駆動方式 | パートタイム4WD |
|---|
| 主要装置 | 可搬型B-3級消防ポンプ |
|---|
| | 1,000W照明装置 |
|---|
| 配備署 | 北部消防署(平成13年12月) |
|---|
はしご付消防自動車(30m級)
| 全長 | 10,700mm |  |
|---|
| 全幅 | 2,490mm |
|---|
| 全高 | 3,350mm |
|---|
| 排気量 | 8,860cc |
|---|
| 駆動方式 | 6×2 4WS |
|---|
| 主要装置 | 30m級油圧はしご装置・リフター装置 |
|---|
| | 伸縮水路管・スーパーインポーズカメラ ほか |
|---|
| 配備署 | 大町消防署(令和2年10月) |
|---|
高規格救急自動車
| 全長 | 5,670mm |  |
|---|
| 全幅 | 1,890mm |
|---|
| 全高 | 2,550mm |
|---|
| 排気量 | 2,690cc |
|---|
| 駆動方式 | フルタイム4WD |
|---|
| 配備署 | 大町消防署(平成30年8月) |
|---|
| 特殊装備 | 対空表示警光灯・衛星電話 など |
|---|
| |
|---|
車両の全面に「再帰性に富んだ反射材」を多用しています。側面には赤と白の市松模様による「バッテンバーグ・マーキング(Battenburg markings:市松模様の反射材の配色を使い分けることにより、災害現場に参集した諸機関の車両を識別できるようにするもの)」を施し、通常の運行はもちろんのこと、万が一車両の電源が失われた場合でも、救急車の存在を示すことにより生存性を高めているほか、消防自動車とは色調を変え、反射材のみで識別が可能にしています。
また、車両後部には「シェブロン・マーキング」を施し、近年増加傾向の被追突事故の防止を図っています。
この「バッテンバーグ・マーキング」、「シェブロン・マーキング」は当広域消防本部が全国に先駆けて導入しています。 |
 |
車両装備の紹介
救助工作車
| 照明装置 |
メタルハライドランプ600W×4灯式。100m離れた場所で新聞が読めるほどの照射力を持つ大型照明装置で、照射角度は左右別々に駆動できます。
電力はフライホイールPTO駆動の発電機(10kVA)から供給されます。 |  |
| 大型油圧救助器具 |
スーパーオートルーカス。油圧救助器具は交通救助には欠くことのできない救助器具で、スプレッダー・カッター・ラムシリンダー・絶縁コンビツールを搭載しています。
トランスミッションPTOを動力とする超高圧油圧ポンプで駆動しますが、ホースリールで延長できるため迅速な救助活動ができるようになりました。 |  |
| 小型移動式クレーン |
フック格納式2.9トン吊り3段ブームの小型移動式クレーンです。 |  |
| 超高圧水噴霧装置 |
オートハイドレックス。車輌のトランスミッションPTOでポンプを駆動し高圧噴霧放水を行う装置で、水タンク120L、泡消化剤20L、放水圧は23.5~25MPです。 |  |
救急車
| ストレッチャー |
最も使用頻度が高い器具で、"メインストレッチャー"と呼ばれることもあります。ケガや病気の方に負担をかけず安全に搬送する担架で、キャスター付きのためスムーズに移動できます。
救急車内では脚を折り畳んで防振架台に固定します。 |  |
| 患者監視装置 |
血圧や脈拍、血液中の酸素飽和度、心電図などを測定する医療機器です。救急隊は、身体の状態や症状に加え、これらの測定値を基に緊急度や病態を判断し搬送先の病院を選定します。
受け入れ先の病院では、救急隊からの事前情報により、必要と考えらる検査や治療の手配を行います。 |  |
| AED |
自動体外式除細動器の頭文字をとった言葉ですが、現在では"AED"が一般的です。心肺停止状態の人に対して電気ショックを行い、心臓の動きを元に戻すための医療機器です。
電気ショックが必要な場合、1秒でも早く処置をすることで回復する確率が高くなることが知られています。 |  |
| 自動式人工呼吸器 |
生命を維持するうえで心臓と肺の働きは最も重要ですが、何らかの理由で呼吸が止まってしまった場合、人工的に肺に酸素を送り込むための機器が人工呼吸器です。
現場ではコンパクトで電源不要な手動式を使うことが多いのですが、救急車内では、送気量や速さなどを設定できる自動式のタイプも使用します。 |  |
| 酸素吸入装置 |
正常な人体は、大気から十分な酸素量を取り込むことができますが、ケガや病気・中毒などにより、取り込む酸素量が低下することがあります。低下した際の症状として
呼吸が苦しかったり顔色が悪くなったりしますが、血中の酸素飽和度で判断することもできます。酸素吸入が必要と判断した場合は、酸素マスクやカヌラを口・鼻に当てて酸素吸入を行います。 |  |
| 電動吸引器 |
意識がない状態で嘔吐したり、喉に食物を詰まらせた場合、自分で吐き出すことができず誤嚥や窒息となります。口や鼻から肺に至る通路のことを"気道"と言いますが、気道内の異物を吸引するための器具が吸引器です。
救急救命士が行う気管内挿管においてもチューブ内の粘液を吸引するために用います。 |  |